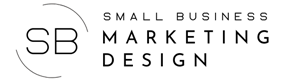ネットショップの上手なキャッチコピーや商品説明は、凄腕の販売員さんのキラートークと同じ。接客上手になれば、それだけでグングン売上が上がるのです。 それでは、ネットショップにおける上手な商品説明文とは、いったいどんなものでしょう。
私が思う『売れる商品説明のコツ』は2つあります。
1つ目は「説明は多すぎず、少なすぎず」。
2つ目は「適切な順番で、先回りする」ことです。
1. 説明は多すぎず、少なすぎず
まずは、コツについて話す前に接客の基本についてお話しします。
ネットではなく実際に店舗に買い物に行くときのことを想像してみてください。
なにかを買いに店舗を訪れたあなた。まず売り場に一歩足を踏み入れて、「いらっしゃいませ」も言われなかったらどうでしょう。
あまり歓迎されていないと感じますよね?
商品がただ置いてあるだけ。店員さんがほとんどいなくて、聞きたいことも聞けない。
そんなお店だったら買い物をやめてしまうかもしれません。
逆に、ずっとついて回られて、頼んでもいないのにセールストークをされたなんてご経験はないでしょうか。
この場合もゆっくり商品を見られず、放っておいて欲しいと感じたり、商品を検討する余裕がないと思いませんか?
あまりしつこければ店を出てしまいたくなると思います。
どちらの場合もあまりいい接客、買いたくなる接客とは言えませんよね。前者の場合は「説明不足」、後者は「説明過多」が問題だといえます。
まず、説明不足のケースについてですが、お客様が買い物をする際には絶対に必要な情報がいくつかあります。
通販のオンラインショップで言うと、「どんな商品なのか」という説明や価格、送料、決済方法が該当するでしょう。
それらがお客様にとって分かりやすく記載されていなければなりません。たまに、オシャレな画像が多様されていて、説明が極端に少ない通販サイトを見かけます。文字も極端に小さかったり、薄い色だったりしますが、あまり親切だとは言えません。いくらオシャレで格好良くても、必要な説明が不足している。
あるいは分かりづらかったら、そこで買い物する気にはなりませんよね。
説明過多についても注意が必要です。
たとえば契約書の規約や説明書のように、細かい文字で大量に説明があったら、読むのが面倒になりませんか?あるいは重要な情報があってもつい見逃してしまうこともあるでしょう。
あまりに情報が多すぎると、重要な情報がその他の情報に埋もれてしまい、気づかれなくなってしまいます。
楽しい買い物の際にあまりずらーっと文字が並んでいたら、面倒に感じる人だっているでしょう。書いてあっても読まれなければ意味がありません。文章量を調整するとともに、大きな文字で見出しやキャッチコピーを書いたり、重要な部分は文字色を変えたりするのも有効です。
大事な情報は「読まなくても目に入ってくる」ように書きましょう。
2. お客様の気持ちを読んで「適切な順番で、先回りする」
店頭ではたとえディスプレイや最初の声かけの反応が今ひとつでも、お客様からの質問に答えたり、反応をみながらトーク内容を選ぶことで挽回できます。
しかし、ネット通販の世界ではそうはいきません。
サイトに掲載しているページの内容=接客なので、お客様が知りたいこと、聞きたいことをすべて先回りして書いておく必要があるのです。
ただし、なんでもかんでも思いついた順に書き連ねるのはあまり得策とは言えません。おすすめはこの3つの順番に沿って書くこと。
Step1:探しているジャンルだと気づいてもらう
たいていの場合、お客様は特定の商品を探しています。
たとえば「子ども用の学習机」「IH対応のフライパン」、化粧品の場合は「日焼け止め乳液」「化粧下地」などでしょうか。
これらは、いわゆる商品のジャンルや概要にあたる情報です。
まず真っ先にこれらの情報を伝えて、「あなたが探している商品はここです!」と気づいてもらいましょう。
Step2:お客様が知りたいことを説明する
お客様に気づいてもらえたら、次は疑問に答えましょう。
「他の商品と比べて何が違うの?」「色は、大きさは?」「素材は? どうやって使うの?」などなど。 お客様が知りたいと思うことをあらかじめ分かりやすくまとめておきましょう。
見出しや文字色などを活用して、「競合の商品と比べて優れているポイント」や「購入の決め手となるポイント」を目立つように、最初に書くのがポイントです。
Step3:不安を解消する
さあ、ここまで来たら最終ステップ。
買う気が高まったお客様が最後に気にするのは、「保証は? 耐久性は?」「どのくらい使えるのか」といったこと。
その不安を解消することで、お客様の背中を押してあげましょう。コンバージョン(購入)の確率はぐっと高まるはずです。
最後にもうひとつ。
オンラインショップのページを改善する際の大切なコツをお伝えしておきます。
それは「商品ページの修正」「バナーの変更」などと考えず、「接客」だと思うこと。
商品ページの修正だと思うと、どうしても「画像がここで、ここにこんな文章を載せて」という固定観念に縛られます。
また、私たち運営側にとって都合のいい情報、載せたい情報ありきで考えてしまいがちです。
そうではなくて、「お客様は」どのタイミングで声をかけられたいか。どこで何が聞きたいのか。
そう考えると、自然とお客様が知りたいタイミングに先回りした、心地よい接客が実現できるはずです。