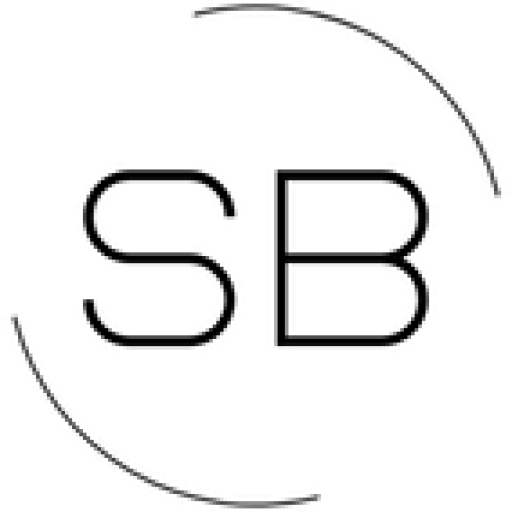「何もしていないのに売上が落ちてきている」
「一番売れ筋だった商品の売上が下がり調子だ」
「ライバルの商品にどんどんシェアを奪われている」
EC通販は競合が多く、変化の激しい世界。このような危機感を抱いている化粧品ブランドさんも多いのではないでしょうか。
売上が下がってしまう要因は様々ですが、
今回はその中でも見落とされがちな原因である
「訴求の劣化」についてお話します。
じわじわ売上を低下させる「訴求の劣化」とは
そもそも、「訴求の劣化」とはいったいどういうことでしょうか。
簡単に言うと、発売当初は目新しかった訴求が時代とともに当たり前になり、魅力を失っていくことを指します。
古くなる、時代に合わなくなると言い換えることもできるでしょう。長年販売している商品やお店で起こりがちな現象ですね。
もう少し噛み砕いてご説明しましょう。 たとえばiPhoneを代表とするスマートフォンのように、今までにないまったく新しい商品が発売したとき、世間ではこのような意識の変化が起こります。
(1)新商品の発売直後 → 人々が興味を持ち始める
(2)商品が世の中に広まっていく → 人々の興味関心が最も高い
(3)商品が「当たり前のもの」として世間に浸透する→ 人々の興味関心が薄れていく
商品が浸透しきった今、「スマートフォンとは」なんて説明をしても、お客様にとってはなんの新鮮味も興味も惹かれませんよね。つまり、これが「訴求が劣化した」状態です。
我々ブランド側もお客様の常識や意識の変化に沿って常に変化をしていかないとまったく魅力のない訴求になってしまうのです。
商品に合わせて3種の訴求を使い分けましょう
「お客様の常識や意識の変化に合わせる」とお話しましたが、では実際にはどうしたらいいのでしょうか。ここでは化粧品ブランドを例に具体的にご説明していきましょう。
(1)新商品の発売直後は「紹介」をする
新商品の発売直後は、お客様はその商品がどんなものか知りません。
特に耳慣れない成分を配合していたり目新しい概念の商品の場合はなおさらです。そんな商品についてお得度をアピールしても、そもそも何者かわからないものを手に取る気にはなれませんよね。
ですから、こういうケースの場合はまず「どんな商品なのか」をていねいに説明し、知ってもらうことがポイントです。
<商品訴求の例>
・ヒアルロン酸の〇倍の保水力! 話題の保湿成分〇〇配合の美容液
・くちびるの温度で色が変わる! 新感覚リップグロス
(2)世の中に広まる時期は「優位性」をアピール
他社も似たような商品を続々と発売。世の中での認知も広まり市場が加熱する時期。
このタイミングで発売直後と同じように「〇〇とは」と説明していても見向きもされません。
お客様が知りたいのは「他社に比べて何が違うのか」「同じような商品の中で自分にピッタリなのはどれか」ということです。
ですから、自分のブランドの商品が他社より優れていることをアピールする必要があるのです。
<商品訴求の例>
・ベタつかない!水みたいにサラサラなのに、紫外線から強力ガードの日焼け止め
・下地いらずなのに崩れにくい! 毛穴レス仕上げのファンデーション
(3)商品が浸透しきったら「新提案」
市場が飽和し、お客様がその商品に慣れきってしまうと、どんなに他社からの優位性をアピールしてもお客様は新鮮味を感じません。
いわばマンネリ化してしまっている状態です。
この状態になると、お客様の興味を再び呼び覚ますためには「商品に対する常識を覆すような新提案」が必要になります。
なにも製品をリニューアルしなくても構いません。ここで大事なのは「お客様の意識」をひっくり返すことです。
ですから、市場動向やお客様の意識をよーく観察することで、新しい訴求を生み出すのです。
<商品訴求の例>
・ヘアケアだけじゃない!爪に、クレンジングに使える植物性万能オイル(椿油)
・高級クリームにも劣らない成分配合の保湿クリーム(ニベア)
ユーザー発の口コミが広まった例にはなりますが、上の2つは既存の商品を見直すことで新たな魅力を発見し、再ブレイクを果たした例です。
意図的に「今までにない訴求・魅力」を打ち出すのは非常に難しいとは思います。しかし、じっくり考えることで商品をロングセラー化する、あるいはさらに爆発的にヒットさせる糸口になるはずです。
たとえ今、安定した売上があったとしても、商品や訴求には必ず「賞味期限」があります。ずっと変化のない売り方を続けていれば、いつか飽きられてしまう日が来るのです。
ですから常に「売れているブランド・お店」そして世の中を観察することで、自身のブランドが「時代に合った訴求」になっているか考えてみることが大切です。
「古いと分かってはいるけど、どう変えたらいいのかわからない」という方は、悩む前にぜひお気軽に私たちにご相談ください。親身にアドバイスいたしますよ。