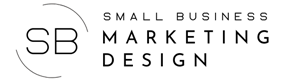はじめに
EC・通販事業のWEB担当者に抜擢されたら、まず最初に向き合うのが「WEBサイトのディレクション」という業務です。
実店舗との大きな違いって、ユーザーが「手に取る」「香りを嗅ぐ」「スタッフに相談する」といった体験ができないという点ですよね。つまり、ネットショップ側が工夫しなければ、ユーザーは迷うばかり。だから導線設計と見せ方の工夫が、本当に大事になってくるわけです。
実は私たちが見てきた中でも、商品自体の強みがあるのに、使いづらいUIや構成がごちゃごちゃしているせいで、その価値が全く伝わらずに離脱していくケースが多々あります。正直、もったいないことが起きています。
「買いたくなる設計」「不安を解消する情報の配置」「スマホでも快適なレイアウト」——こういった視点を常に持ちながら、WEBサイト全体を設計・監督していくのが、ディレクション業務の本質です。
ディレクションって結局なに?
WEBサイトのディレクションとは、サイト構成やデザインの方向性を考えて、デザイナーやエンジニア(コーダー)と連携しながら、最終的なページが完成するまでの一連の流れを統括することです。
建築業界の例で言うと、「設計士」と「現場監督」を一緒にしたようなポジション。つまり、以下のようなことを考えるのが基本的な役割です:
「どんなユーザーに向けて、どんな見せ方で、どんな順番で情報を出すか」
ちなみに、これを専門職としている人が「WEBディレクター」なんですが、小規模な通販サイトの場合は担当者がこのディレクター業務を兼任することが多いですね。体力がいりますが、その分やりがいもある仕事です。
最近のトレンドを押さえておく必要がある
スマホ対応は「対応」ではなく「最優先」
2025年現在、ECサイトへのアクセスの7割以上がスマートフォンから来ています。もう「PCサイトを先に作ってスマホに落とし込む」という時代は終わりました。スマホを中心に考えて設計する——モバイルファーストUXが当たり前になっています。
具体的には、こんなことを気にしながら設計します:
- ボタンのサイズ感は実際の指で押しやすいか?
- スクロール量が多くて、途中で誰もが離脱しそうになってないか?
- ファーストビューだけで、このサイトは信頼できそうと伝わっているか?
こういう細かな点を見落としてしまう担当者も多いですが、スマホの画面でボタンが小さいままだと、どんなにいい商品でもタップミスで離脱されてしまいます。意外と離脱率に響いてくるポイントです。
ランディングページは「結果が出やすい」から手を抜けない
広告やSNSから流入したユーザーが最初に見るのがLP(ランディングページ)です。特に新規顧客獲得の場面では、最初の数秒で「あ、これ自分に関係あるな」って思わせられるかがすべて。だからこそLPのディレクションは非常に重要です。ワイヤーフレームの段階から、以下を意識しておく必要があります:
- ファーストビュー案をいくつか作って、どれが一番離脱が少ないか検証する準備
- キャッチコピーとビジュアルが本当にマッチしているか
- 「購入までの流れ」がわかりやすく、スムーズになっているか
LPは成果が数字に出やすいので、ディレクションの腕の見せどころでもあります。
ワイヤーフレーム作成が、ほぼすべてと言ってもいい
WEBディレクション業務の中で、最も時間と頭を使うのが「ワイヤーフレーム(設計図)」の作成です。
これは、WEBページの構成や情報配置を目に見える形にした図面で、デザイナーやエンジニアに対して「こういう構成で作ってほしい」と伝えるための重要なツール。簡単に言えば、ページの「骨組み」ですね。
ワイヤーフレームに使うツールって?
正直、専用のデザインツールは必須ではありません。ExcelでもPowerPointでも、あるいは紙に手書きでもOK。大事なのは以下の2点に尽きます:
「伝えたいことの重みづけ(優先順位)」が整理されているか
そして
「ユーザーがどう流れていくのか」が視覚的に理解できるか」
見出し・画像・キャッチコピーなどが「読み飛ばしても伝わる」ような設計を心がけておくと、後々の成果に繋がってきます。

出典: キラメックス株式会社
実践的な、ワイヤーフレームのコツ
情報の優先順位を明確にする
当たり前と思われるかもしれませんが、実はできてない案件が本当に多いんです。単に写真とテキストを順番に並べただけでは、見た人にとって「で、結局何が重要なの?」となってしまいます。
意識しておくべきポイント:
- 一番伝えたい「ベネフィット」はどこに配置する?
- 比較表やクチコミは、ユーザーの購買心理でいうとどの段階で出す?
- 購入ボタンは1回だけ?それとも複数回出した方が効果的?
「何をどこで伝えるか」に優先順位をつけて構成することが大切です。これがしっかりしていれば、デザイナーも「あ、この設計思想が理解できた」と納得して仕事を進められます。
デザインはしない。でも「雰囲気」は考える
ワイヤーフレーム自体は設計図ですから、凝ったビジュアルデザインは不要です。ただし、ページ全体の雰囲気や色合い(トンマナと呼びます)については、ディレクター側である程度の方向性を示す必要があります。
例えば:
- メインカラーをなぜそれに決めたのか、ちゃんと理由を持っているか?
- 写真は清潔感を出すのか、高級感を狙うのか、親しみやすさを重視するのか?
- 書体は柔らかい印象か、堅い印象か?
こういう「理由を持った設計」こそが、実はプロのディレクションで欠かせない部分です。
最近はPinterestやInstagramで参考イメージをビジュアル共有するスタイルも一般的になってきていますね。「こんな感じの世界観で」と伝える時は、言葉より画像の方が伝わりやすいと思います。
2025年、生成AIとの付き合い方
ここ最近、WEBディレクション業務でも生成AIを活用するケースが増えています。
例えば:
コピーのたたき台をAIに作らせて、複数案の中から良さそうなものを選んで、さらに磨き上げる。LPのキャッチコピー案をAIに生成させて、A/Bテストの素材にする。ペルソナ設計のヒントとしてAIに「このターゲットの検索意図は何か」を質問する。
ただし、ここが重要なんですが——すべてをAI任せにしてはいけません。AIが出してきたものは「発想の補助」程度に考えておく。「芯を食った設計」には、人間の戦略的判断が絶対に必要です。
アクセシビリティが、けっこう大事。
最近、視覚障害がある人や高齢のユーザーを含むすべての人が快適に使えるサイト設計が、EC業界でも重視されるようになってきました。
具体的には:
- 画像にalt属性をきちんと記述すれば、音声読み上げに対応できる
- 色覚障害への配慮として、文字と背景のコントラストが十分か確認する
- フォーム項目を適切にグループ化してあげると、ユーザーのストレスが減る
実はこれらは、SEO評価にも直結する項目です。ディレクションの段階からこういったことを意識しておくと、長期的には「このサイトは信頼できるな」というブランド信頼にも繋がります。
結局、設計がすべて
WEBディレクションって、単なる「指示出し」ではありません。
ユーザー心理を読み解いて、適切な導線を描いて、魅力が伝わる構成をデザインに落とし込む——。実は高度な「戦略と設計」の仕事なのです。
モバイルファーストの視点、LPO(ランディングページ最適化)、生成AIの活用、アクセシビリティへの配慮。こういった最新の視点も踏まえながら、売れるECサイトを作るための「設計者」としてのチカラを磨いていく。
正直なところ、WEB担当者の道は楽ではありませんが、その分、やり甲斐のある仕事だと思います。