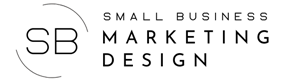「ネットショップの商品説明文って、何を書けばいいか悩む」
「キャッチコピーを考えるのが苦手」
「商品の魅力がちゃんと伝わっていない気がする…」
こんな悩みを抱えているEC担当者さま、結構多いですよね。実は、商品説明文やキャッチコピーって、ネットショップにおける”接客トーク”そのものなんです。
実店舗で販売員が「この商品、今の季節にぴったりですよ」と声をかけるように、ページ上でも言葉が接客を担う。そこをちゃんと理解できていないと、どんなに良い商品でも売上につながりません。
2025年の今、ユーザーの購買行動はもっと複雑になっています。SNSで見かけた、InstagramのUGC(ユーザーが投稿した写真や動画)経由で来たとか、検索から来たとか、経路もバラバラ。だからこそ、「商品説明=接客」だと本気で捉えて設計する視点が、ますます重要になっているんです。
この記事では、2025年のトレンドも踏まえながら、「売れる商品説明とキャッチコピー」の作り方を、できるだけ分かりやすく解説していきます。
情報の”塊”ではなく、流れる接客として設計する
商品ページって、多くの人が「情報を詰め込む場所」だと勘違いしています。でも本当は違う。実店舗での販売員の動きを思い出してみてください。
最初に「いらっしゃいませ、どんな商品をお探しですか?」と声かけする。次に「こういう点が他の商品と違うんです」と説明する。最後に「大丈夫、返品もできます」と不安を解消する。この流れがあるんです。
ネットショップも、この同じ”流れ”を作る必要があります。
説明が少なすぎる場合のデメリット
商品画像だけで、サイズも素材も書いてない。使い方も不明。…こういうページは、実店舗で言えば”店員が全然説明しない店”と同じです。今のECユーザーは情報が足りないと、すぐに別のサイトへ去ってしまいます。
実際、スマホユーザーの話を聞いていると「スクロール3回以内に必要な情報が見えなきゃ、他を探す」って言う人ばかり。ですから最低限、ユーザーが知りたい情報は揃えておくべきです:
- 商品の用途と特徴
- サイズ・素材・仕様
- 使用シーンや季節性
- お手入れ・使用上の注意点
- 配送・保証・返品可否
反対に、説明が多すぎる問題
長文がずらーっと並んで、小さい文字で埋め尽くされてるページ。ああいうのも正直、ユーザーは敬遠してしまいます。
ここで大事なのは、”読む情報”と”見る情報”のバランスです。
実際に成果の出ているページを見ると、どうしているか。見出しで先に結論を出す。大事なポイントは太字にする。箇条書きにして構造を見やすくする。アイコンや吹き出しで視認性を上げる。こういう工夫がされてるんですよ。
つまり「読ませる」のではなく、「見れば分かる」という意識が大切。これが視認性と説得力を両立させる秘訣です。
ユーザーが知りたいことを”先回り”して説明する大切さ
ここで重要な気づきがあるのですが、実店舗の販売員って何をしてるかというと、常に”先回り”してるんですよ。
お客さまが「これ、どのくらい持ちますか?」と聞く前に、「このタイプは大体3年はもちますね」って言っておく。「サイズは合いますか?」と聞かれる前に、測り方を説明しておく。そういう工夫をしているわけです。
ネットショップでも、まったく同じことをする必要があります。ただし、対面ではなく、文章と構成で”先回り”させるわけですね。
で、実際に効果的な商品ページを見ていると、だいたい以下の流れになってます。
ステップ1:「これ、あなたが探してた商品ですよ」と気づかせる
冒頭のキャッチやタイトルで、ユーザーが「あ、これ自分に関係ある」って感じるかどうか。ここで感じれば、スクロールして詳しく見てくれます。感じなければ、即離脱。
例えば:
- 「●●な悩みを持つ方におすすめの〜」
- 「2児のママが”ようやく見つけた”○○」
- 「一人暮らし×時短×節水=この炊飯器!」
こういう感じですね。
ステップ2:「ほかの商品と、何が違うんですか?」への答え
ここで大事なのが、ちょうど2025年あたりから主流になってる「生活文脈で語る」っていう表現です。
昔は「5L容量、ステンレス製」みたいにスペックを並べていました。でも今は違う。「家族4人分のカレーが一気に仕込めて、洗うのも簡単」みたいに、”使った人の生活”を見せるんです。
数字じゃなくて、その先にある”生活”を伝えることが本当に重要になってます。
ちなみに2025年はUGC(ユーザーが投稿した写真や動画)との組み合わせが最強だったりします。文章だけじゃなく「実際に使った人の声・写真・動画」を見せることで、信頼度と購買意欲がぐんと上がるんです。InstagramやTikTokの埋め込み、実際の使用レビュー写真カルーセルとかですね。
ステップ3:「買っても大丈夫か」という不安を消す
ここが意外に大事なのですが、ユーザーって心理的に「本当に失敗しないだろうか」って不安を抱いてます。特に高い商品や初めての購入だと顕著です。
だから:
- 返品保証・無料交換の有無
- 使い切っても返金可(サブスク商品など)
- 販売実績やレビュー評価
- 医師や専門家のコメント
こういった”安心材料”を先に用意しておく。これがコンバージョンに直結します。
「感情×スペック」の組み合わせが、2025年の売れ方
ここから先は、ちょっと最近気づいたトレンドの話なのですが。
数字やスペックだけを並べてても、人は動きません。「最大90dBの高音質スピーカー」って書いても、心に響かない。でも「小さな体に驚くほどの迫力。手のひらサイズで、部屋がライブ会場に変わります。」って書くと、急に欲しくなる。
同じ商品説明でも、感情に寄り添う表現と事実で後押しする、この組み合わせがとっても大事です。
例:
✗ スペック中心の書き方: 最大90dBの高音質スピーカー
〇 感情×スペックの書き方:
「小さな体に驚くほどの迫力。手のひらサイズで、部屋がライブ会場に変わります。」もう一つ:
✗ 重さ120g、折りたたみ式
〇 「旅行バッグの隙間にすっと入る、片手で持てる軽やかさ。」
ここが、AIが絶対に生成できない部分です。”ユーザーの生活に入り込む表現”。これが今後のライティングの本質になってきてます。
「感覚ワード」だけじゃ、もう通用しない
昔は「ふんわり」「しっとり」「安心設計」みたいな、ふわっとした言葉が重宝されていました。今でも使いますが、それだけじゃ弱い。いま大切になってきたのは、その先の具体性です。
- 「朝の通勤時間に使うなら、このタイプ」
- 「○○とセットで使うと最強」
- 「これ1本で時短、片手で持てる」
使用シーン、組み合わせ方、行動喚起。”具体的な状況”と”数字”をセットにする表現が、今は支持されているんです。
生成AIを上手に使って、効率と品質を両立させる
ちなみに2025年のEC業界は、ChatGPTやNotion AIを活用した「ライティングの半自動化」が、もう一般化してきています。
実装ポイント:
- 商品特徴を箇条書きで入力 → 説明文を数パターン生成
- キャッチコピーの候補をAIで出す → 人間がトーン調整
- A/Bテストをする場合も、ChatGPTでパターン作成
「0→1」の速度が圧倒的に早まります。PDCAの回転も高速化する。
ただし、注意点がひとつあります。AIの生成文は”情報の正確さ”や”トーン”に注意が必要。必ず人間の最終チェックが必要です。下手をすると、AIっぽさが前面に出てしまいます。
結局のところ、何が大事なのか
「画像を置いて、スペックを箇条書きにして…」
こんな”設置型”の商品ページは、もう通用しません。正直に言うと、これでは競争に勝てません。今のユーザーが求めてるのは、「会話しているかのように感じる商品説明」です。
- お客様が知りたいことを先回りして
- 不安に感じるポイントを先に伝えて
- 期待を超える提案を文章で伝える
この”思いやりの接客”が、売れるECサイトの根幹です。
接客の気持ちで、キャッチコピーと説明文を設計する。それが、あなたのネットショップを”売れるお店”に変えていく最大の武器となります。