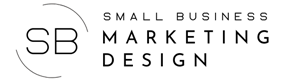「お客様目線で考えて」と言われても、正直なところ何を変えたらいいのか分からない。15年以上にわたってEC事業に携わり、業界大手のEC部門で責任者を務めた経験から言うと、こうした戸惑いはEC担当者の間では本当に多い。実際に支援している中小企業のチーム内でも、よくこんな場面に出くわします。
「ページ構成を改善したつもりが、若い社員から『なんか古い』と指摘されてしまった」「そもそも何を強調すべきなのか…」。特に男性中心のチームだと、若い女性顧客のニーズを正確に把握できないまま施策を進めてしまうケースが目立ちます。
アパレルの担当をしていた時代、30代後半の女性ターゲットだと思い込んでいた商品が、実は20代後半の独身女性に売れていたことに気づかされました。このズレを発見したのは、お客様の生の声に目を向けてからです。
記事では、ペルソナマーケティングを2025年時点の最新トレンドまで含めて整理します。ターゲットとペルソナの違い、複数ペルソナの設計方法、AI・行動データの活用まで――EC現場でそのまま使える実践的な考え方をお伝えします。
なぜ今、ECサイトにペルソナマーケティングが必要なのか
多様な価値観が共存する現在、ただ漠然と「30代女性向け」と決めるだけではマーケティングは機能しません。むしろそんな粗いイメージだけで判断すると、競合との差別化もできずに埋もれていくばかりです。
「30代女性」という外的属性だけでは、その人が何に悩み、何に価値を感じるのかが見えません。結果として「誰にも刺さらないコンテンツ」が生まれてしまいます。
この記事では、以下の3つを明確にします。
- ターゲットとペルソナの本質的な違い
- 2025年の標準となった「複数ペルソナ×LTV視点」での設計方法
- 実際にペルソナ設計がもたらす具体的な売上変化
ターゲットとペルソナの違いを整理する
ターゲット=外的属性でのグループ分け
マーケティングで使われる「ターゲット」とは、年齢、性別、職業、地域といった外的属性で「40代女性・東京都在住・パート主婦」のようにグループ化することを指します。
テレビCMや新聞広告が主流だった時代には、これで十分でした。マス広告はそもそも「広い層に同じメッセージを届ける」ことが前提だったから、粒度の粗さは問題にならなかったのです。だからこそ、今でもマーケティングの教科書にはターゲット設定として書かれています。
ただし、現代のEC市場でこれだけでは足りません。
ペルソナ=一人の生活者としての具体像
一方、ペルソナというのは、ターゲットを一人の具体的な人物像にまで深掘りしたもの。単なる属性ではなく、その人のライフスタイル、趣味や価値観、家族構成、どんなSNSを使っているのか、何に悩んでいるのか――こうした生活感のある細部まで詳細に設計します。
ペルソナを「実在する人間」と同じレベルで描写することで、初めて「その人に向けた施策」を考えられるようになります。
化粧品のEC運営をしていた時代、「乾燥肌の女性」という曖昧なターゲットからペルソナに変えました。その結果、「夕方になると目元がつっぱるあなたへ」という、その人の日常的な悩みに直結したコピーが生まれました。曖昧なターゲット設定では、こうしたニュアンスは決して出てきません。
2025年のペルソナマーケティングは「複数ペルソナ×LTV視点」が前提
単一ペルソナではカバーしきれない理由
従来のやり方だと「1ブランド=主力ペルソナ1人」が定番でした。「うちはこの人のために作ってます」という感じですね。ただし率直に言うと、それでは今は通用しません。
なぜなら、同じECサイトを訪れるお客様でも、新規客と既存客では欲しい情報が全く異なるからです。カゴ落ちしかけている人への対応も、3回目の購入を検討している人への対応も変わります。
2025年は「マイクロペルソナ」(細分化された複数の人物像)で考えるのが主流になっています。特にEC領域では「顧客がどれくらいの期間、どれくらいの金額を使ってくれるのか」を示すLTV(顧客生涯価値)という視点が必須になってきました。
LTV視点でフェーズ別ペルソナを設定する
実務的には、お客様の購買フェーズごとに異なるペルソナを設定します。以下の表は、EC運営の現場で実際に機能している分け方です。
| フェーズ | ペルソナ例 | マーケティング施策 |
| 新規顧客 | SNSから流入したZ世代女性(22歳、上京したばかり) | SNS特化のバナー、動画広告、限定クーポン、ファーストバイヤー向けメール |
| リピーター | 定期購入している40代主婦(娘が小学生、月1回程度購入) | メール配信、レビュー投稿依頼、会員限定セール情報 |
| 離反予備群 | 3日前にカゴ落ちした男性(ギフト購入層) | LINE配信、リカバリー施策、クーポン再提示 |
このテーブルの考え方が理解できると、施策の精度が大きく変わります。
リピーター対応を変えるだけで売上が変わる
実務経験の中で強く実感するのは、リピーター層への対応力の重要性です。
業界では「リピーター層への対応を変えただけで購買額が30%上がった」という事例が数多く報告されています。ただし、重要な注釈があります。この数字は、リピーター層の行動データを分析し、その層が「何回目の購入時に何を欲しているのか」を理解した上での施策によって初めて実現するもの。単に「既存顧客を大切にしよう」という心がけだけでは到達できません。
日用雑貨のECサイトで経験したのは、2回目購入までのタイミングが非常に重要だということ。1回目購入から2回目購入までの間に、「この店は信頼できる」という認識を作れるかどうかで、3回目購入の確率が大きく変わりました。
AIと行動データで変わった、2025年のペルソナ設計
行動データに基づく「実在ペルソナ」へ
ここからが2025年ならではのポイントです。Google Analytics 4やClarityといった分析ツールとAIが融合して、ペルソナ設計は属人的な作業ではなく行動データに基づく設計へ進化しています。
かつては「営業担当者の勘」や「担当者の想像」に頼る部分が大きかった。それが今は、実際のお客様の行動データから「実在するペルソナ」を抽出できるようになったのです。
具体的には以下のようなことが可能になりました:
- Shopify × GA4の組み合わせなら、「カート放棄率が高い年代」「購買額が高い層の閲覧動線」が自動で抽出される
- KARTE(カルテ)やHubSpotといったMAツールではデータをスコアリングして、「このグループが好反応」というのを機械学習で自動判定してくれる
結果として「誰に向けたコンテンツを強化すべきか」「どのグループが最も利益に貢献しているか」が数字で見える化されます。勘に頼らず、事実ベースで判断できるようになったわけです。
ただし、ここで留意点があります。より高度な分析(BigQueryエクスポート、CRM連携など)には時間とコストがかかります。私たちが支援する中小企業の中でも「高度な機能は使いこなせない」という課題を頻繁に耳にします。
中小企業でも始められる現実的なレベル
「ツール費用が高くて…」と敬遠する傾向が強い中小企業ですが、実は無料から始められる範囲で十分な効果が期待できます。
Shopifyなら無料で基本的な分析機能がついていますし、Clarity(Microsoft製)も無料プランがあります。別に高度なことをしなくても、最初はこの程度で十分です。
「どの層がどのくらい閲覧・購入しているか」を見る程度でも、大きな気づきが得られます。ペット用品のECサイトで実験した時は、GA4の無料レポートだけで「想定していた40代女性が購入層なのに、実は30代男性(彼女へのギフト購入)が最大ボリュームだった」ことが判明しました。この一つの気づきが、その後のコンテンツ戦略を大きく変えました。
完璧な分析を求めるのではなく、「小さく始める」という姿勢が、実務では何より大切です。
ペルソナ設計でECサイトは具体的にどう変わるのか【3つの効果】
① 刺さるコンテンツ・コピーに変わる
ペルソナなしだと「乾燥肌用美容液」みたいなフラットな商品説明になります。
でもペルソナで相手の悩みが見えてくると、こんなコピーが生まれます:「夕方になると目元がつっぱるあなたへ。35歳からの保湿ケア習慣」。
共感のレベルが全く違う。営業トークではなく、友達からのアドバイスに近い感覚になるのです。
実務的には、この変化は売上数字に直結します。同じ商品を同じ広告費で宣伝しても、コピーが変わるだけで反応率が1.5〜2倍になることは珍しくありません。
② チームの判断軸がそろう
これも地味ですが、おそらく最も重要な効果です。
クリエイティブ案や広告文を作成するときに、「担当者の主観」だけで判断すると方向性が分裂しがちです。Aさんは「もっとポップに」、Bさんは「落ち着きが必要」みたいな感じです。
ペルソナがあれば「小野真由さん(35歳、時短勤務のワーキングマザー)ならどう感じるか?」という共通の物差しで議論できます。判断がシンプルになり、チーム内の認識ズレが激減します。
食品(仕出しサービス)のECサイト運営では、この効果は絶大でした。営業、デザイン、カスタマーサポートの3部門が「ペルソナ像」を共有することで、個別には相反する要望が一つの方向に統合されました。
③ 改善のスピードが上がる
施策の結果が「誰に響いたのか」見えるから、原因分析が楽になります。
A/Bテストでバナー2種類の反応が異なったときも、ペルソナの価値観と照らし合わせて「あ、この年代・ライフステージはこういう表現を好むんだ」と要因が分かる。迷いながらやるのと比べると、PDCAが圧倒的に回しやすくなります。
ECでのペルソナの作り方【実践ステップ】
お客様から直接聞いた声を分析することが、最も信頼度の高いペルソナを作る方法です。「何となく想像で作る」のではなく、既にある顧客の声から組み立てることが重要です。
ステップ1:顧客の”生の声”を集める
素材は周りにいっぱい転がっています。
- 商品レビューや口コミ
- アンケートの記述回答
- サイト内検索ワード(「〇〇の代わりに」「〇〇を使っている人が感じること」など)
- LINE・メールでの問い合わせ内容
- SNSでのハッシュタグ投稿
- カスタマーサービスへの連絡内容
これらはお客様が自然に発信している情報です。営業トークではなく、本当に困っていることや欲しいことがダイレクトに表現されています。
ステップ2:共通する悩み・行動パターンを整理する
集めた素材を眺めていると、繰り返し出てくるキーワードやシーン、感情が見えてきます。
例えば化粧品で分析すると「朝は時間がない」「子どもがいると自分の時間が取れない」「効果を実感したい」といった共通テーマが浮かぶ。これを抽出することが次のステップの基礎になります。
ステップ3:1人の人物像としてプロフィール化する
集めたデータから、架空の人物像を設計します。既存の顧客データを参考にしながら、こうした形で整理します:
ペルソナ例:小野真由(仮名)
- 年齢:35歳
- 職業:時短勤務のワーキングマザー
- 家族構成:夫・小学2年の娘
- ライフスタイル:平日夜にスマホで買い物。土日は子ども優先で自分の時間は限定的
- 価値観:コスパ、見た目の良さ、子育てとの両立が何より大事
- 日々の悩み:疲れているのに肌がボロボロ、でも手入れに時間をかけられない
- 使用デバイス:主にスマホ(寝る前の30分が自分時間)
- SNS:Instagram、LINE
このレベルまで詳細に設定することが、その後の施策の精度を大きく左右します。
ステップ4:具体的な施策に落とし込む
ペルソナ設定そのものが目的ではなく、実際の施策に反映させることが全てです。
LP導入文での共感スタート 「朝は時間がない、でも肌がボロボロ…」こうした共感から入ることで、スクロール率が変わります。
商品名・コピーで用途やシーンが伝わるように 「美容液」ではなく「夜寝る前5分のスキンケアセット」というシーン記述によって、ペルソナの行動に直結します。
広告文で課題解決を強調 「忙しいママこそ、簡単ケアで肌を整える」という、ペルソナの制約条件に寄り添った表現を心がけます。
実務では、こうした細部の工夫が積み重なって初めて反応が変わります。
ペルソナだけでは足りない──パーソナライズとの掛け合わせ
ペルソナ=共通言語、パーソナライズ=一人ひとりへの最適化
ここまで読んでくれた方は気づいているかもしれませんが、現在はペルソナとパーソナライズの融合が鍵になっています。
ペルソナで全体の方向性を決めつつ、実際の配信や表示では「個別最適化」を組み合わせるのです。
ECでのパーソナライズ施策例
- Web接客ツールで過去の閲覧履歴に応じてバナーを差し替える
- メール配信で購入履歴別に件名・内容を変える
- LINEでセグメント別に配信内容を切り替える
こうした施策は、一見するとペルソナ設計と矛盾するように見えるかもしれません。しかし実は相補的です。
ペルソナ×パーソナライズで成果が変わる理由
ペルソナが「チームの共通言語」になって、パーソナライズが「一人ひとりへの配慮」になる。この両立ができると、成果が大きく変わります。
「このブランド、私のことを分かってくれてる」「なんか私っぽい」――そういう感覚的なフィット感が購入に直結するのです。
まとめ|「このブランドは私のことを分かってくれている」をどう作るか
2025年は、商品のスペックだけで選ばれる時代ではありません。
機能や価格だけなら、オンラインなら同等の商品はすぐに見つかります。競争の軸が「フィット感」へ移った今、ペルソナ設計がその土台になるのです。
もし今「どんな言葉が刺さるか分からない」「社内で判断が割れてばかり」と感じたら、まずは1人の理想のお客様像をじっくり描いてみてください。その一歩から、見える景色が違ってきます。
15年以上のEC運営経験から言うと、この「ペルソナ設計」という基本作業を丁寧にやるかやらないかで、その後の売上は確実に変わります。
ペルソナの作成や活用にお悩みなら、ぜひ私たちの無料相談からお問い合わせください。
► 無料相談はこちら
※ 「業種別ペルソナ設計テンプレート」や「レビュー分析から作る共感ワード抽出ガイド」などの支援資料は、提供に向けて準備中です。整い次第、ご案内させていただきます。