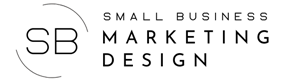「制作会社から上がってきたデザインが、なんか違う」
「『もっとかっこよく』と伝えたら、逆に見づらいページになった」
ネットショップの運営現場で、このような「制作の事故」は日常茶飯事です。
しかし、15年以上の現場経験から断言します。上がってきたデザインが微妙な原因の9割は、デザイナーの腕ではなく、店長(発注者)の「オリエン(指示)」の曖昧さにあります。
デザイナーはエスパーではありません。「売れるページを作って」と言われても、何が「売れる」の定義なのか、誰に売りたいのかが分からなければ、彼らは「とりあえず綺麗なページ」を作るしかありません。
本記事では、無駄な修正ラリーをなくし、初回からクオリティの高いページを作らせるための「EC特化型オリエンテーション」の極意と、今すぐ使える「構成指示テンプレート」を公開します。
1. 良いオリエンとは「正解」を最初に渡すこと
オリエン(オリエンテーション)とは、制作開始前に「何を作るか」をすり合わせる会議のことですが、多くの店長はここで「要望」だけを伝えてしまいます。
- × ダメなオリエン: 「40代向けの化粧水です。高級感のある感じで、あと楽天で1位とりたいので強めに推してください」
- ○ 売れるオリエン: 「ターゲットは肌のくすみに悩む45歳女性。競合A社よりも保湿力が高い点を、数値データ(グラフ)を使って証明し、信頼感のある『紺色』をベースにデザインしてください」
前者は「感想」ですが、後者は「設計図」です。
制作を依頼する際は、「デザイン以外の全て(構成・ターゲット・訴求点)」を決めてから渡すのが、発注者の責任です。
2. これだけ埋めればOK!「最強のオリエンシート」5項目
私が実際に現場で使用している、制作指示書(オリエンシート)の必須項目です。これを埋めて渡すだけで、デザイナーの迷いが消えます。
① 【誰に?】ペルソナ(ターゲット)の解像度を上げる
「30代女性」では不十分です。
- NG: 30代女性
- OK: 3歳の子育て中で、自分のスキンケアに時間をかけられない32歳主婦。スマホで夜22時に閲覧することを想定。
② 【何を?】USP(独自の売り)を言語化する
「高品質」などのふわっとした言葉は禁止です。
- NG: 国産で高品質
- OK: 〇〇県産のシルクを100%使用しており、他社製品より摩擦係数が20%低い(データあり)。
③ 【競合は?】参考サイト(ベンチマーク)を指定する
言葉で伝えるより、実物を見せるのが最速です。
- デザインの参考: 「色使いはこのサイトのような落ち着いたトーンで」
- 構成の参考: 「説明の流れはこのサイトのこの部分を真似したい」
※ただし「丸パクリ」はNGです。「要素」を参考にさせます。
④ 【ゴールは?】コンバージョン地点を明確にする
- 目的: 「お試しセット(500円)」の購入なのか、「定期コース(3,000円)」の契約なのか。それによってボタンの色や配置が変わります。
⑤ 【素材は?】写真とテキストは「完全支給」が鉄則
「いい感じの写真を探して使って」は事故の元です。
必ず「使用する写真」と「掲載するテキスト」はフォルダにまとめて渡しましょう。デザイナーに「素材探し」や「ライティング」をさせないことが、コストダウンと品質アップの秘訣です。
3. 2026年流「AI」を使った“構成案”の時短テクニック
「構成案を作る時間がない」「文章が思いつかない」
そんな時は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを「優秀なアシスタント」として使いましょう。
【店長が使うべきプロンプト例】
「私はECサイトで[商品名]を販売します。ターゲットは[ターゲット層]です。
この商品の魅力は[特徴]です。
ユーザーが購入したくなる、LP(ランディングページ)の構成案を作ってください。
『キャッチコピー』『問題提起』『解決策』『証拠』『オファー』の順で、具体的な文章案も入れてください」
出力された構成案をWordやExcelに貼り付け、微調整してデザイナーに渡せば、プロレベルの構成指示書が3分で完成します。
【重要】AIは「嘘」をつくことがあります。必ず人間が検品してください
ここで1つだけ絶対に守ってほしいルールがあります。それは、「AIの出力結果をそのままコピペして渡さないこと」です。
AIはもっともらしい嘘(ハルシネーション)をついたり、法律(薬機法や景品表示法)を無視した表現をしたりすることがあります。また、あなたの店舗特有の「熱量」や「お客様への愛」までは再現できません。
AIが作るのはあくまで「たたき台」です。 「事実に間違いはないか?」「自社の言葉になっているか?」を必ず店長自身の目で確認し、魂を吹き込んでからデザイナーに渡してください。
4. デザイナーを潰すNGワード集(フィードバックの作法)
デザインが上がってきた時、修正指示(フィードバック)の出し方でデザイナーのモチベーションは大きく変わります。
× 「なんか違うんだよね」「もっとシュッとさせて」
感覚的な言葉は禁止です。「違う」なら「何と比較してどう違うのか」を言語化してください。
× 「ここを赤にして、ここを大きくして」
デザインの素人である店長が、具体的な修正指示(手を動かす指示)を出すと、全体のバランスが崩れてダサくなります。
「解決したい課題」を伝えて、修正方法はプロに任せましょう。
- 良い指示: 「文字を大きくして」ではなく、「このキャッチコピーが目立たないので、スマホで見た時に一番最初に目がいくように調整してほしい」
5. スマホ実機でのチェックは「義務」
2026年現在、PCのデザインはどうでもいいと言っても過言ではありません。
納品されたデザインは、必ず「自分のスマホ」で確認してください。
- 指でスクロールした時に、気持ちよく読めるか?
- 購入ボタンは押しやすい位置にあるか?
- 文字サイズは小さすぎないか?(16px以上推奨)
PCのモニターで見ている景色と、お客様がスマホで見ている景色は全く別物です。
まとめ:良いページは「良い発注」から生まれる
「制作会社にお金を払っているんだから、全部やってくれて当たり前」
そう思っているうちは、絶対に売れるページはできません。
ECサイトの制作は、「設計士(店長)」と「大工(デザイナー)」の共同作業です。
設計図が適当なのに、良い家が建つはずがありません。
まずは、今回ご紹介した「オリエンシート」を使って、あなたの頭の中にある「売れるイメージ」を言語化することから始めてみてください。
そのひと手間が、制作費を無駄にせず、売上というリターンを最大化する唯一の方法です。
「指示の出し方がわからない」とお悩みの方へ
「頭では分かっているけど、構成案を作る時間がない」
「今の制作会社のクオリティに不満がある」
もしそのようなお悩みをお持ちなら、ぜひ一度ご相談ください。私たちはコンサルティングであると同時に、15年のEC運営経験を持つ「元店長」の集団です。
ふんわりとしたご要望からでも、「売れる構成」に落とし込みます。撮影・デザイン・コーディングまで一気通貫で代行も可能です。
あなたの商品の魅力を100%引き出すページ制作を、私たちがサポートします。
► 無料相談はこちら